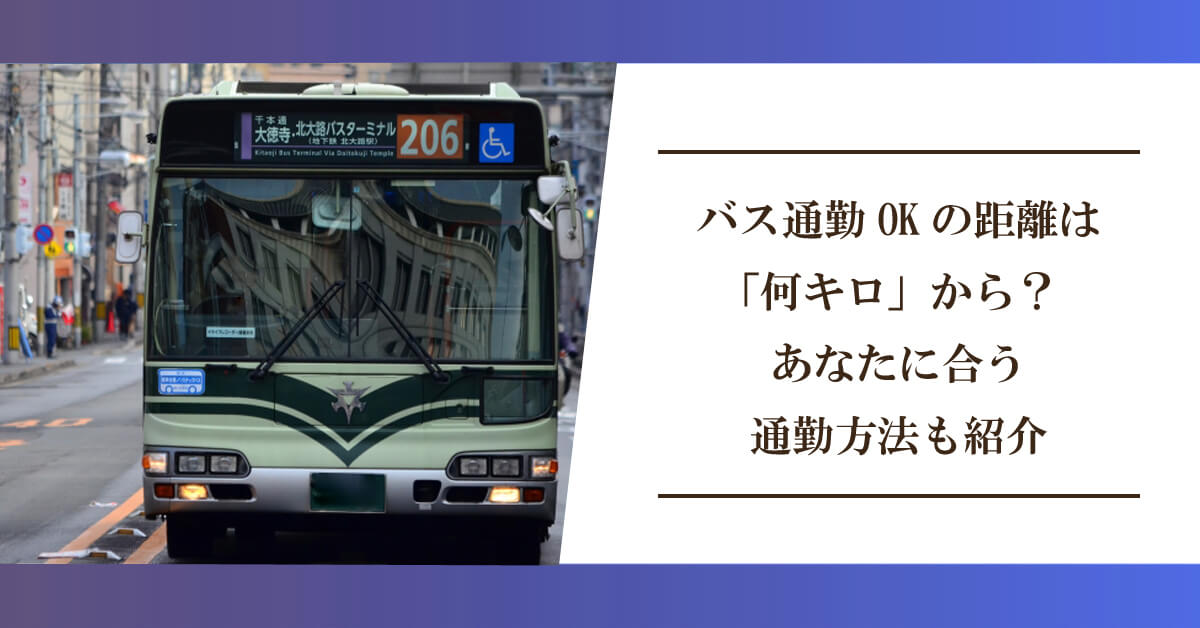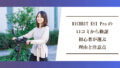バス通勤は何キロからOKなのか、通勤手当や交通費はどこから支給されるのか――。
こんな疑問を持って「バス通勤 何キロから」と検索していませんか?

実はこのテーマ、会社や自治体によって基準がバラバラだったり、「通勤手当は何キロから?」「2キロ未満は手当なしって本当?」など細かい悩みが尽きません。
この記事では、バス通勤が認められる目安の距離や「バス通勤 何キロから手当が出るのか」といったリアルな基準、さらに健康面や快適さのメリット・デメリットまで、分かりやすくまとめました。
通勤手当や交通費の支給基準、バス通勤が向いている距離、他の通勤手段との違い、快適に通うコツまで徹底解説します。
これからバス通勤を始めたい人も、「何キロからOKなのか迷っている」「会社のルールが分からない」と悩んでいる人も、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
バス通勤は何キロから?距離と目安を徹底解説
バス通勤は、実際どれくらいの距離から始める人が多いのでしょうか?
この章ではバス通勤を始める目安の距離や、よくあるケースをわかりやすく解説していきます。
それでは、実際にどのくらいの距離でバス通勤に切り替える人が多いのか、リアルな目安や周囲の実情も交えて紹介していきますね。
バス通勤は2キロからが一般的
結論として、バス通勤が認められるのは、基本的に「2キロ以上の距離」になっています。
理由はシンプルで、「それくらい歩いてね」というのが企業側のスタンスだから。
たとえばですが、
- 自宅から駅まで1.4キロ
- 最寄駅から職場まで1キロ
この距離だと、原則としてバス代は支給されませんね。
逆に言えば、2キロを超えればバス通勤も手当の対象になる会社が増えてきます。
このように「2キロルール」は、通勤手当の支給や非課税扱いの基準にもなっています。
だからこそ、「自分の通勤距離、本当に2キロ以上ある?」って、一度しっかりチェックしておいた方がいいですよ。
バス通勤に切り替える人のリアルな理由
バス通勤に切り替える理由は、人それぞれ。
一番多いのは、通勤距離が伸びて「もう歩きや自転車は無理だ…」と限界を感じるパターンですね。
たとえば、
- 転勤や事業所の移転で「駅から会社まで1キロ以上歩くことになった」
- 家が駅から遠くて「雨の日は毎回ずぶ濡れでテンション下がる…」
みたいな人が多いです。
あと、会社都合で勤務地が遠くなったり、家の近くに新しいバス路線ができたりして、乗り換える人も増えていますよ。
ほかにも、以下のような人もバス通勤を選ぶのも珍しくありません。
- ケガや持病、妊娠・出産、加齢など体力的な理由
- 子育てや介護で「朝は少しでもラクしたい!」と感じて
このように、通勤ラッシュのストレスだったり、坂道の多さだったり、小さな子ども連れだったり、理由は本当に十人十色。。
最近だと、会社や自治体が「バス通勤OKの制度」をどんどん用意してくれるケースも増えてきました。
必要だと感じたら、遠慮せず相談してみるのがいいですね!
バス通勤で気をつけたい通勤手当・交通費の基準
バス通勤を始めるなら、絶対に知っておきたいのが通勤手当や交通費の基準です。
会社からしっかり交通費をもらうために、必ず以下のポイントをチェックしておいてください。
一つずつ解説しますね。
2キロ未満は手当なしが多い理由
通勤手当って、2キロ未満だとほとんど支給されないのが現実です。
なぜなら、多くの企業や自治体が「2キロ未満=徒歩で十分」と判断しているため。
国税庁の通勤手当の非課税ルールでも、片道2キロ未満は非課税対象外となっています。

たとえば、家から会社までが1.4キロであっても、たとえ坂道であったとしても、就業規則で「2キロ以上」と決まっていれば手当は原則支給されません。
この背景には、
- 会社としても全員に手当を出すとコストがかかる
- 国のルールに合わせて運用したほうが手続きが簡単
など、現実的な事情もあります。
もし「どうしてもバス通勤じゃないと無理!」という場合は、個別事情を人事や上司に相談するのが一番です。
とはいえ、まずは「2キロ以上が通勤手当のボーダーライン」という基準をしっかり押さえておくと損をしませんよ。
企業・自治体で異なる支給基準
バス通勤の通勤手当は「2キロから」と聞きますが、正直なところ会社や自治体によって全然違います。
その理由は、各社・各自治体ごとに就業規則や賃金規定で細かくルールを設定しているからです。
たとえば、
- A社 → 最短経路で1.5キロから支給
- B社 → 駅から職場まで1キロ以上
みたいな感じで。
しかも、自治体や公的機関になると「1.6キロから」「2キロから」みたいな、数百メートル単位で変わることもあります。

さらに「電車+バス」「バス+徒歩」など、複合ルートを使う場合「どこからどこまでが支給対象なの?」とあいまいになって、あとでトラブルになる人も多いです。
このへんは、全部「就業規則」「賃金規定」に書かれてるので、必ずチェックしておきましょう!
課税・非課税のルールと金額
通勤手当には「課税・非課税」のルールがあるので、しっかり理解しておくことが大切です。
その理由は、通勤手当がすべて非課税になるわけではなく、国税庁のルールで非課税の範囲や金額が細かく決められているからです。
具体的には、以下のように設定されています。
- バスや電車などの公共交通機関を使う場合は、月15万円までが非課税
- マイカーとか自転車通勤だと、通勤距離ごとに非課税の上限額があり
特に、2キロ未満だと手当が全額課税対象、2キロ以上なら下記の範囲内で非課税です。
【片道通勤距離と非課税上限額(月額)】
| 片道通勤距離 | 非課税上限額(月額) |
|---|---|
| 2キロ未満 | 0円(全額課税) |
| 2キロ~10キロ未満 | 4,200円 |
| 10キロ~15キロ未満 | 7,100円 |
| 15キロ~25キロ未満 | 12,900円 |
| 25キロ~35キロ未満 | 18,700円 |
| 35キロ~45キロ未満 | 24,400円 |
| 45キロ~55キロ未満 | 28,000円 |
| 55キロ以上 | 31,600円 |
もしバス定期券の金額が上記の上限を超えたら、その分だけ所得税がかかります。
なんとなくで「大丈夫っしょ」と思ってると損するので、事前にちゃんと調べましょう。
就業規則のチェックポイント
通勤手当をきちんと受け取るためには、あなたの会社の就業規則や通勤手当規定を必ずチェックすることが大切です。
なぜかというと、
- 支給の対象距離
- どの経路が認められるか
- 定期券の扱い
- 申請のルール
こういう細かい部分は、会社ごとに全然ちがいます。
たとえば、バスが必須かどうかとか、複数のルートがある場合は「一番安くて合理的な経路」を使うよう決まってたりします。
会社都合で異動になったときや営業所が移転した場合は、特別なルールができたり、例外的な措置が取られることもあるんです。

手続きミスで損しないためにも、分からないことはそのままにせず、一つずつクリアにしていくと後悔しなくて済みますよ。
バス通勤に適した距離・5つのメリット
バス通勤に向いている距離や、バスならではのメリットは以下の5つです。
それぞれの距離ごとの快適さやメリットを、体験談も交えて解説しますね。
2キロ以上は快適バス通勤の目安
バス通勤がラクになったなと感じるのは、2キロ以上の距離が目安になります。
理由はシンプルで、2キロという距離って、歩いたら20分以上、自転車でも10分くらいかかりますよね。
これが毎日になると、やっぱり天気や荷物次第でジワジワ体力が削られるからです。
たとえば、
- 夏の暑い日
- 雨や風が強い日
- 仕事の資料や荷物が多い日
といったときは、「やっぱりバスがあって助かった!」と感じることが本当に多いです。
「2キロ」というラインを境に、バス通勤の快適さがぐっとアップするので、ぜひ遠慮なく活用してみましょう!
3〜5キロは通勤効率も良い距離
3〜5キロの距離になると、バス通勤の効率がグッと良くなります。
なぜなら、これくらいの距離になると徒歩や自転車ではかなり大変になってきて、朝からムダに疲れてしまうからなんです。
バスを使えば、通勤時間はだいたい10〜20分で済むことが多いですし、都市部でもこの区間は渋滞や遅延がそこまで多くありません。

特に郊外や住宅地から都心に向かう場合、バスの本数やルートも豊富なので、「今日はどのバスに乗ろう?」と選びやすいのも嬉しいポイント。
3〜5キロの距離なら定期券を使って交通費をお得にできるし、途中で買い物やちょっとした寄り道もバスだからこそ気軽にできます。
もし今の通勤がしんどいな…と感じている人は、まずは3〜5キロ圏内でバス通勤を試してみてください。
きっと朝から余裕ができて、毎日が少しラクになりますよ!
10キロ以上は長距離ならではのメリット
10キロ以上の通勤距離になると、バス通勤のメリットを最大限に感じやすくなります。
なんでかというと、ここまでの距離になると徒歩や自転車はもう現実的ではありません。
電車や自家用車と比べても、バスならではの
- 移動時間の活用
- 座ってラクに過ごせる快適さ
を実感できる場面が増えるんですよ。
たとえば、バスの直通便や空いている時間帯を選べば、
- 読書
- 仮眠
- 仕事の準備
など、自分の時間として有効活用できます。
たしかに最初は「渋滞したらどうしよう…」って不安もあると思います。

でも、慣れてくると「この交差点は混むから10分前に出発しよう」みたいに、自分なりの攻略法も身につくんです。
また、長距離通勤の場合は会社の手当額も増えることが多く、交通費の面でも安心です。
このように、通勤距離が長い人ほど、バス通勤の快適さやメリットを実感しやすいので、ぜひ上手に活用してみてくださいね。
健康や体力面でのメリット
バス通勤には、実は健康や体力面でもちゃんとメリットがあるんです。
その理由は、歩きや自転車通勤だと朝から体力をゴリゴリ削られますよね。
でも、バスを使えば体力温存モードで出社できるので、心にも体にも余裕を持って1日を始められるわけです。

たとえばですが、「駅まで歩くだけで出社前からヘトヘト…」という人はわりといます。
でもバス通勤なら、その消耗を抑えられ、朝から余力バッチリの状態で仕事に向かえます。
しかも、バス停までの短い徒歩が“ちょうどいい運動”になって、運動不足の心配もいりません。
さらに、天候や季節による体調不良(熱中症・風邪・花粉症など)も避けやすくなりますし、雨の日や雪の日でも安心して通勤できるので、精神的なストレスも大きく減ります。
このように、自分のペースで無理なく通勤できるのが、バス通勤の健康維持につながる大きなポイントですよ。
ストレス軽減や時間活用のコツ
バス通勤の最大のメリットは、通勤時間を快適に過ごせて、心の余裕が生まれることです。
というのも、歩きや自転車だと、
- 急な雨で服がビショビショ
- 汗だくで職場に到着
と地味に積み重なりますが、バスなら、こういう面倒ごとを減らせますよ。
たとえば、
- 本やスマホで情報収集したり
- SNSや動画をチェックしたり
- リラックスして仮眠をとったり
こんな感じの自分なりのルーティンを作っている人が多いです。
朝の時間を有効活用できることで、出社前に心を落ち着けたり、一日の予定を整理したりできるのも大きな魅力ですね。
バス通勤の4つのデメリット・注意点
バス通勤には良い点だけでなく、知っておきたいデメリットや注意点もあります。
デメリットや注意点は以下の4つです。
「思ったよりも大変だった…」と後悔しないためにも、事前にしっかりチェックしておきましょう。
通勤時間が長くなりやすい
バス通勤を始めると、「思ったより通勤時間が長くなった…」と感じることが多いです。
これは、バスが停留所ごとにちょこちょこ止まるから、どうしても移動に時間がかかりやすいんですよね。

たとえば、自転車や徒歩なら信号待ちだけでサクサク進む道でも、バスだと何度も停車があるので「もう少し早く着けたらいいのに!」と感じる人も多いはず。
しかも、
- バスの発着時刻
- 乗り継ぎ
- 待ち時間
まで含めると、トータルで見ると通勤所要時間が伸びやすいのも事実です。
朝の渋滞やラッシュに巻き込まれると、予定より到着が遅れたりします。
だからこそ、時間に余裕を持って家を出るのが安心です。
ギリギリに出るのをやめておくと、遅延にも焦らずに済みますよ。
混雑や遅延のストレス
バス通勤で避けて通れないのが、「混雑」と「遅延のストレス」です。
なぜなら、
- 朝夕のラッシュ
- 道路の混雑
- 悪天候
など、どうしてもバスが混みやすい時間帯が存在するからなんですよね。
たとえば、主要なバス路線ではバス停に長蛇の列ができたり、満員で1本待たないと乗れないことも珍しくありません。

本数が少ないエリアだと、1本逃しただけでかなり待つことになり、「なんで今日に限って…」とイライラしてしまうことも。
こういったストレスを少しでも減らすコツは、とにかく“前もって行動”すること。
- 1、2本早いバスに乗る
- 始発停留所から狙う
- 混雑時間をずらす
など、ほんの少し工夫するだけで気持ちがだいぶラクになりますよ。
健康リスクや体の負担
バス通勤には「健康リスク」や「体の負担」がつきものです。
その理由は、
- 長時間同じ姿勢でバスに座っていたり
- 混雑時に立ちっぱなしになったり
すると、腰痛や肩こり、足のむくみなどが起きやすくなるからなんですよね。

たとえば、毎日1時間近くバスに乗っている人だと、「最近なんだか体がだるい」「肩がバキバキ…」なんて感じたことがある人も多いと思います。
さらに、座れない日はカバンを持ったままバランスを取らないといけなかったり、体が思っている以上に疲れるものです。
こうした健康リスクを減らすためには、
- バス停まで歩いたり
- 乗車中に軽いストレッチをしたり
- 荷物をできるだけ軽くする
などの小さな工夫がとても大切です。
ときには帰り道だけ徒歩や自転車にしてみるなど、無理せずバランスを取るのもおすすめですよ。
通勤手当や交通費の課題
バス通勤を考えるときに意外と見落としがちなのが、「通勤手当や交通費の課題」です。
前述でも話しましたが、多くの会社で「2キロ以上」など一定の距離や条件を満たさないとバス代が支給されなかったり、手当の支給ルールが会社ごとにバラバラだからです。
たとえば、
- 距離の測り方が分かりにくい
- 支給基準があいまいで手当がもらえなかった
- バスと電車を併用しても手当が一部しか出ない
なんてケースもあります。
また、税法上の非課税限度額を超えると課税対象になるため、「思ったより手取りが増えない」と感じることもあります。

こうしたトラブルや損を防ぐためには、「入社前」「異動前」「申請前」など、できるだけ早い段階で通勤手当のルールや必要書類をきちんとチェックすることが大切ですよ!
他の通勤手段と比較!最適な通勤距離の選び方
バス通勤だけでなく、他の通勤手段と比較して自分にピッタリな距離や方法を選ぶコツを紹介します。
「今の通勤方法、本当に自分に合っているのかな?」と感じたら、ぜひいろいろな選択肢をチェックしてみてください。
毎日の通勤がもっと快適で楽しくなりますよ!
徒歩・自転車・電動キックボードとの比較
通勤距離が2キロ未満なら、徒歩・自転車・電動キックボード、このあたりが最適解です。
なぜかというと、距離が短い場合はバスや電車よりも自分のペースでサクッと動けるし、交通費もほとんどかからないから。
それぞれの特徴を表にまとめると、こんな感じ。
【徒歩・自転車・電動キックボードの通勤手段の特長】
| 通勤手段 | おすすめ距離 | メリット | デメリット | 利用者の声 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩 | ~2キロ | ・運動不足の解消 ・健康的 ・気分転換になる | ・雨の日や猛暑日はつらい ・荷物が多いと大変 | 「健康志向な人におすすめ」 「リフレッシュできる」 |
| 自転車 | 2~5キロ | ・移動時間の短縮 ・自由度が高い ・気軽に使える | ・坂道や交通量に注意 ・駐輪場の有無を要確認 | 「坂道がなければ快適」 「運動にもなる」 |
| 電動キックボード | 5~10キロ | ・バスや電車より自由度が高い ・体力を使わず移動可能 ・交通費節約 | ・法律やルールを要確認 ・充電や駐輪場所の管理が必要 | 「交通費がゼロになった」 「坂道もラク」 「満員電車を回避できた」 |
自分の距離・天気・体力・ライフスタイルに合わせて“最適な手段”を選ぶのが大事。
バス通勤だけじゃなくて、こういう新しい選択肢もどんどん試してみると、もっと快適な通勤ができますよ。
電動バイク・車サブスクという選択肢
片道10キロ以上の通勤だと、バスじゃなくて電動バイクや車のサブスクも選択肢に入ってきます。
それぞれのそれぞれの特徴を表にまとめると、以下のとおりです。
【電動バイク・車のサブスクの通勤手段の特長】
| 通勤手段 | おすすめ距離 | メリット | デメリット | 利用者の声 |
|---|---|---|---|---|
| 電動バイク | 10キロ~20キロ | ・静かで経済的 ・充電がカンタン ・エコで維持費も安い | ・バッテリー残量に注意 ・悪天候時はやや不便 | 「バスより快適だった」 「維持費も節約できた」 |
| 車サブスク | 10キロ~ | ・維持費やメンテ費用が込み ・必要な時だけ使える ・家族のライフスタイルに柔軟対応 | ・渋滞・駐車場の確保 ・ガソリン代など追加コスト | 「家族の送迎にも便利」 「自由度が一気に上がった」 |
距離が長い人ほど、自分のペースで通勤したいと思うはずなので、そういう人はバス以外の選択肢も本気で検討すべき。
正解は毎日変わるし、「いま自分と家族に合う通勤方法は何か?」を柔軟に選び直してみてくださいね。
自分に合った通勤手段の見極め方
自分に合った通勤手段の見極め方って、これが絶対正解みたいな方法はありません。
ここを勘違いして「一度決めたら変えちゃいけない」と思い込むと、結局しんどくなって続かなくなりますよ。
なぜかというと、
- 天気
- 通勤ルート
- 仕事の忙しさ
- 自分の体力
なんかで日々どんどん変わるからです。
たとえば、昨日まで気持ちよく自転車通勤できてたのに、急に「今日はもう無理…」と感じることも普通にあります。

そういうときは我慢しないで、その日の気分や体調で選ぶのが一番のコツ。
「毎日疲れ切って帰ってるな」とか、「移動中にもう少しリフレッシュしたいな」みたいな自分の本音を優先した方が、結果的にストレスも減ります。
会社の交通費規定や手当も大事ですが、「今日はバス、明日は自転車」みたいに柔軟に選んでもOKですよ。
まとめ:バス通勤の距離・手当・快適さの目安
バス通勤は何キロから可能か、そして何キロから手当が出るのかは会社や地域によってさまざまですが、一般的には「2キロ以上」から認められるケースが多いですね。
バス通勤のメリットは、体力の温存や天候に左右されない快適さ、移動時間の有効活用などがあります。
逆に、混雑や遅延、手当の条件や健康リスクなど注意点もあるので、就業規則や手当基準をしっかりチェックすることが大切です。
また通勤距離やライフスタイルに合わせて、最適な方法を選びましょう。
| 距離 | おすすめ手段 | ポイント |
|---|---|---|
| ~2キロ | 徒歩・自転車 | 健康・節約重視、天候注意 |
| 2~5キロ | バス・自転車・電動キックボード | 坂道・荷物多い日はバスが便利 |
| 5~10キロ | バス・電動キックボード・電動バイク | バスなら定期券でコスパ◎ |
| 10キロ~ | バス・電動バイク・車サブスク | 体力温存、移動時間を自分時間に |
まずは実際に動いてみて、「これなら続けられる!」というスタイルを少しずつ見つけていくのがおすすめです。
会社のルールがよくわからない場合は、総務や人事にサクッと相談してみましょう。
行動してみて初めて「自分だけの快適な通勤スタイル」に近づけますよ!