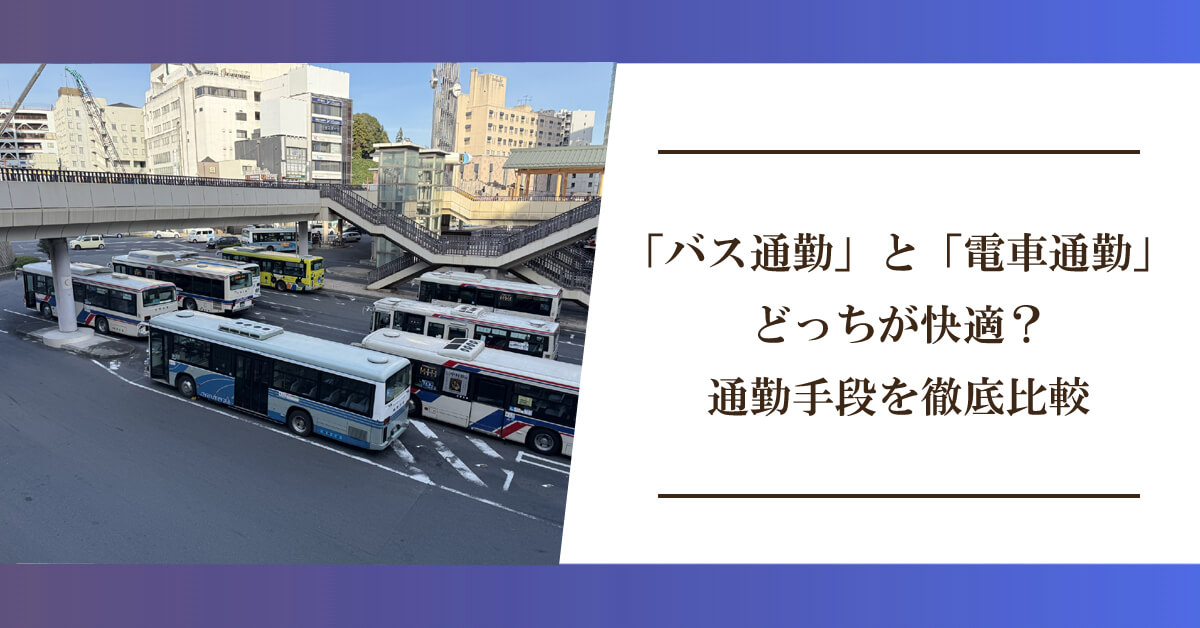毎朝、学校や仕事に行くとき「バスと電車のどちらがラクかな?」「お金や混み具合、何を大事にすればいいのかな?」と迷う人は多いと思います。
通勤や通学の方法を選ぶときは、毎日の疲れやお財布事情、さらには健康にも影響するので大事です。
バスはドアツードアに近い一方で渋滞の不安があり、電車は定時性に優れるものの満員ラッシュが課題になるなど、一長一短がはっきりしています。
この記事では、バスと電車での通勤を比べて、かかるお金や混み具合、天気の影響、健康面までをわかりやすく解説します。
「自分にはどっちがが合うかな?」と悩んでいる方は、このまま読み進めて、あなたにぴったりの通勤スタイルを見つけてくださいね。
バス通勤と電車通勤のどっちが快適か比較
通勤のしやすさは、手段ごとの特徴を知り、自分の生活スタイルに合うかどうかを比べることが大切です。ここでは、バスと電車を選ぶときに押さえておきたい5つのポイントをまとめました。
- バス通勤のメリットとデメリット
- 電車通勤のメリットとデメリット
- 通勤ストレスの違いと影響
- 時間の正確さと遅延リスク
- バスと電車の交通費、会社の支給制度でどう変わる?
ひとつずつ見ていきましょう。
バス通勤のメリットとデメリット
バス通勤のメリットとデメリットを分かりやすくまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自宅や職場近くのバス停を利用できれば、ドアツードアに近い移動が可能 | 一般道路を走行するため、渋滞や事故の影響を受けやすい |
| 乗り換えが少なく雨の日でも負担が軽い | 地方や郊外では運行本数が少なく、待ち時間が長くなる |
| 運賃や定期代が電車より安い場合が多い | 早朝・深夜の便が限られ、勤務シフトと合わない場合がある |
| 車内で座れる確率が高く、身体的な疲労を抑えやすい | ダイヤ改正で減便が発生すると、通勤計画を見直す必要がある |
| バス専用レーン採用区間では渋滞回避が期待できる | 無料Wi‑Fiが未整備の路線が多く、車内での学習や仕事が難しい |
まずバス通勤のメリットを解説しますね。
メリット
バス通勤には、環境や経済面、利便性など、複数の観点からメリットがあります。
家や会社のすぐ近くにバス停があると、歩く距離が短くなり、ほかの乗り物に乗り換える必要もありません。そのため、雨が降ったり雪が積もったりしても移動がラクになります。
また、交通系ICカードをかざすだけで乗り降りできるので、小銭を出す手間がかかりません。都市によってはバス専用の道があり、車の渋滞に巻き込まれにくい場合もあります。
さらに、電車ほど混まないことが多く、座席に座れる可能性が高いので、長い時間立って疲れることが少なくてすみますよ。
デメリット
一方で、デメリットも明確に存在します。
バスは一般道路を走るので、車が多い時間帯や事故があったとき、そして雨や雪の日には予定より遅れやすいです。とくに人や車がたくさん集まる大きな道路を通るルートでは、時刻表どおりに着かないことがよくあります。
また、国土交通省の調査(参照:国土交通省)によると、都会とくらべて地方では走るバスの数が少ないです。1時間に1~2本しか来ないこともあるので、1本乗りそびれると30分から1時間も待つことになりかねません。
特に郊外や住宅地においては、早朝や深夜の便が限られています。前もって時刻表やスマホのアプリでダイヤを確かめる必要があります。
もう一点、バスの中にはインターネットにつながるWi-Fiが付いていない場合が多く、移動中に調べものや勉強をしにくいことも覚えておきましょう。
電車通勤のメリットとデメリット
電車通勤のメリットとデメリットをわかりやすくまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 定時運行率が高く出社時刻を計画しやすい | ラッシュ時の乗車率が高く圧迫感を覚えやすい |
| 数分おきに列車が来るため乗り遅れてもリカバーしやすい | 立ちっぱなしが続くと疲労やストレスが蓄積しやすい |
| 移動中に読書やスマホ学習で時間を有効活用できる | 定期券が高額になり自己負担が発生する可能性がある |
| 駅周辺に店舗が多く用事をまとめて済ませやすい | 人身事故・信号トラブルなど突発運休がゼロではない |
| 天候や渋滞の影響を受けにくく安定して移動できる | 混雑時は感染症への不安が高まりやすい |
電車通勤のメリットとデメリットを詳しく解説しますね。
メリット
電車通勤の一番のメリットは、ほぼ時間どおりに走ることです。
国土交通省の「都市鉄道の整備状況」によると、日本の大きな都市を走る電車は約95%の確率で予定どおりに動いているので、バスや車よりもずっと頼りになります。しかも朝や夕方の混む時間でも、数分待てば次の電車が来るため、乗り遅れてもすぐに別の電車に乗れます。
また電車の中では、座れればスマホで動画を見たり、本を読んだりして時間を有効に使えます。さらに、駅の近くにはコンビニや薬局などのお店がたくさん並んでいるので、行き帰りにちょっとした買い物ができて便利です。
同じ路線を毎日使っていると、自然にその地域のことにも詳しくなり、生活の一部として電車通勤が定着していきますよ。
デメリット
一方で、電車通勤には困る点もあります。
朝や夕方のいちばん混む時間は、人がぎゅうぎゅうに乗っていて身動きがとれません。特に首都圏では乗車率が180%を超えることもあり(国土交通省より)、長いあいだ立ったままで体がとても疲れます。

隣の人との距離が近いので、風邪やインフルエンザが流行するときは不安を感じる人も多いでしょう。
それから、電車の定期券はバスより高くなることが多く、会社が交通費を全部払ってくれない場合は自分で足りない分を出さなければなりません。路線によって割引があるかどうかを、あらかじめ調べておくと安心ですね。
さらに、人身事故や信号の故障で急に電車が止まることもあり、どんなに時間どおりに走る路線でも絶対に遅れないわけではありません。通勤が大幅に遅れたときに、別の行き方を考えておいたり、会社が在宅勤務や時間をずらして働く制度を用意しているかどうかを確認しておくと、いざというときに慌てずにすみますよ。
通勤ストレスの違いと影響
通勤で感じるストレスは、乗り物の特徴と自分の性格が重なって起こります。一言で言えば、
- バス通勤 → 遅延の不安
- 電車通勤 → 混雑の圧迫感
といった感じがストレスの中心です。
バスでは、事故や渋滞で長く止まると「会社に遅れるかも」と焦りやすくなります。しかもバスを待つあいだは外に立っていることが多く、暑さや寒さで体が疲れることもあります。
電車は、人がいっぱいの車内で音やにおいが気になりやすく、立ちっぱなしで足や腰がだるくなりがちです。駅の中を歩くときも、人の流れや階段で気を使う時間が長くなりますね。
以下に違いを比較表としてまとめました。
| 項目 | バス通勤 | 電車通勤 |
|---|---|---|
| 主なストレス要因 | 渋滞や事故による遅延 / 屋外での待機 | 満員状態の圧迫感 / 騒音・におい |
| ストレスが高まる場面 | 始業前の遅延発生時 | ラッシュピークで乗車率が上がる時間 |
| 身体への影響 | 車内揺れや長時間座位で酔いやすい | 立ち続けによる足腰の疲労 |
| 精神面への影響 | 到着時刻が読めず焦燥感が強まる | 密集空間でイライラや不安が蓄積 |
| 対策の自由度 | 早く家を出て余裕を確保しやすい | 時差出勤や乗車位置調整で混雑を緩和 |
まず、あなたが「電車やバスが遅れるとイライラするタイプ」か、それとも「人がぎゅうぎゅうにいる場所が苦手なタイプ」かを考えてみましょう。時間が多少ずれても平気ならバスでも問題ありませんし、会社が出勤時間をずらせる制度を用意しているなら、混んでいない時間に電車へ乗ることでラクになりますよ。
また、働き方にもいろいろ選択肢があります。
- 出勤時間を自由に決めやすいフレックスタイム
- 家で働けるテレワーク
を利用すれば、渋滞や満員電車のピークを避けることができます。
通勤で感じるストレスは夜の睡眠や家に帰ったあとの元気にも影響するので、乗り物の選び方と働き方を上手に組み合わせ、自分にとっていちばん負担の少ない通勤方法を考えてみてください。
時間の正確さと遅延リスク
通学や仕事に行くとき、「時間どおりに着けるかどうか」はとても大切です。電車とバスでは、その安心感が少し違いますよ。
一言で言えば、
- 電車通勤 → 定時性
- バス通勤 → 道路事情による揺らぎ
が鍵となる移動手段です。
電車は、朝の混む時間でも数分おきに次の列車が来ることが多いので、もし1本逃してもすぐ次の電車に乗れます。また、スマホのアプリで遅れの情報や「遅延証明書」をすぐに確認できるため、「学校や会社に遅れそう!」というときも理由を説明しやすいです。
一方バスは、渋滞や信号待ちに左右されやすく、一本遅れると待ち時間が一気に伸びるケースもあります。特に郊外路線では「1時間に1本」など本数が限られるため、余裕を多めに見込む必要が出てきます。
以下に違いを比較表としてまとめました。
| 項目 | 電車通勤 | バス通勤 |
|---|---|---|
| 時間正確性 | 定時運行率が高く、数分〜十数分の遅れで収まる傾向 | 道路混雑で到着が大幅に遅れる可能性がある |
| 遅延要因 | 人身事故・信号トラブル・天災 | 渋滞・事故・信号待ち・悪天候 |
| 便の頻度 | ラッシュ時は2〜3分間隔 | 地方では1時間に1本の例も |
| 遅延証明 | オンライン発行が整備され勤怠報告しやすい | 発行サービスがない事業者も多い |
| 代替手段 | 振替輸送や別路線利用でリカバーしやすい | 迂回路が限られ、タクシー利用が増えがち |
このように、電車は「時間が正確」、バスは「道路状況しだい」という違いがあります。
自分の生活リズムや地域の交通事情を考えながら、もし遅れたときにどう動くかもイメージしておくと、あわてずに通学・通勤できますよ。
バスと電車の交通費、会社の支給制度でどう変わる?
「バスは必ず安い」「電車は高い」と思われがちですが、実際には勤務エリアや会社の支給ルールで負担額は大きく変わります。
まずは代表的な通勤手段と定期代の目安、そして企業側の交通費規定との相性を比べてみましょう。
| 通勤手段 | 1か月定期の目安(都内) | 会社支給との相性 | 補足ポイント |
|---|---|---|---|
| バス定期券 | 6,000〜7,000円 | 「最安経路」で支給する企業と好相性 | 定額料金が多くコスト管理しやすい |
| 電車定期券(単一路線・近距離) | 10,000〜12,000円 | 支給上限が1万円前後の場合は超過分が自己負担 | 乗換なしなら時間も読める |
| 電車定期券(複数路線・中長距離) | 12,000〜18,000円 | 上限設定のある会社では自己負担が増えやすい | 速達性は高いがコスト比は上昇 |
| テレワーク手当(在宅勤務中心) | 0〜5,000円前後/月 | 「通勤手当を支給しない」企業が増加 | 出社頻度次第で最安になる場合も |
コストを抑えたいなら、通常はバスの定期券が安くすみます。でも、会社が「いちばん短いルートの交通費だけ払います」と決めている場合、電車の定期券でも全額を出してもらえることがあります。
反対に、上限額が決まっている会社で複数路線をまたぐ電車定期を選ぶと、自己負担が大きくなるため要注意です。
最近はテレワーク比率が高まったことで、会社が通勤手当をなくして「在宅勤務手当」を出すところも増えています。週に数回しか出社しない働き方では、従量課金のICカード利用に切り替えるほうがコストを抑えやすいケースもありますよ。
- 通勤の回数
- 駅までの距離
- 会社の交通費のルール
などをまとめて考え、定期券代を“決まった出費”と決めつけず、ときどき見直すことがお金を守るコツです。
バス通勤と電車通勤、どっちがあなたに合うか解説
毎日の通勤手段は、混雑の度合い・運動量・天候リスク・費用など、さまざまな要素で快適さが変わります。ここでは、自分に合う方法を見極めるために押さえておきたい5つの視点を整理しました。
- 電車とバス、混雑による通勤快適度はどう違う?
- 通勤向きのバス路線は見つかる?
- 電車通勤で運動不足は解消できる?
- 渋滞や天候に左右される影響度
それぞれ詳しく解説しますね。
電車とバス、混雑による通勤快適度はどう違う?
通勤時の混雑は、体力・気力の消耗度を大きく左右します。
かんたんに言うと、
- 電車通勤 → 超満員
- バス通勤 → 席が取りやすいかどうか
が快適さのカギです。
電車は座れるチャンスが少なく、立ちっぱなしで疲れやすいですが、本数が多いので時間を少しずらせば混雑を避けられることがあります。
バスは始発の停留所から乗れば席に座りやすい一方、定員いっぱいで乗れず、次のバスを待つことになる場合もあります。どの時間やルートを選ぶかがとても大切ですね。
以下に違いを比較表としてまとめました。
| 項目 | 電車通勤 | バス通勤 |
|---|---|---|
| ピーク時混雑率 | 150〜180%超の路線もある | 路線により差はあるが電車より低め |
| 座れる可能性 | 低い(特に都心部は立ち乗り前提) | 始発停留所利用で座れる確率が高い |
| 主なストレス要因 | 圧迫感、接触トラブル、荷物の圧迫 | 積み残し待ち時間、渋滞中の閉塞感 |
| 回避策 | 時差出勤、各駅停車や先頭車両を選ぶ | 早便や始発バス利用、運行本数が多い路線選択 |
| 快適度に影響する要素 | 路線の本数・駅の設備・乗換回数 | 路線のダイヤ・地域の道路事情・車両定員 |
混雑をなるべく減らしたい人は、始発駅や始発バスを利用して早めに乗車し、席を確保するのがおすすめです。もし人が多い場所が苦手なら、出勤時間をずらしたり、家で仕事をしたりして混む時間帯を避けるとラクになります。
どちらの方法を選ぶにしても、自分が使うルートや時間帯がどれくらい混むのかを前もって調べ、空いている便や車両の場所を知っておくと、毎日のストレスをぐっと減らせますよ。
通勤向きのバス路線は見つかる?
バス通勤のしやすさは「本数」と「走る時間帯」に大きく左右されます。
都市部では5〜10分おきに来る路線もあり、乗り遅れてもすぐ次便へ乗れる安心感があります。ただ、郊外や地方へ行くと早朝と夜間は1時間に1本以下というケースも珍しくなく、一本逃すだけで遅刻リスクが跳ね上がります。
さらに近年は運転手不足で減便が続く地域もあり、将来のダイヤ変更まで視野に入れておきたいところです。
| 地域区分 | 通勤時間帯の本数(目安) | 平均間隔 | 始発・最終の傾向 | 将来的な減便リスク |
|---|---|---|---|---|
| 都市部幹線 | 6〜12本/時 | 5〜10分 | 始発04:30頃・最終24:00前後 | 低いがダイヤ改正あり |
| 郊外住宅地 | 2〜4本/時 | 15〜30分 | 始発05:30頃・最終22:30前後 | 中 ※一部で本数縮小 |
| 地方中心市街 | 1〜3本/時 | 20〜60分 | 始発06:00頃・最終21:00前後 | 高い 減便・路線統合が進行 |
| 郊外・山間部 | 1本/時以下 | 60分以上 | 始発07:00頃・最終19:00前後 | 非常に高い 廃止候補になる場合も |
始業に遅れたくない方は、都市部でも始発便や早めの便を利用すると座席を確保しやすく、遅延リスクの回避にもつながります。郊外や地方でバス通勤を選ぶなら、ダイヤ改正情報を定期的にチェックし、最終バスの時刻と減便予定を把握しておくと安心ですよ。
電車通勤で運動不足は解消できる?
電車で通うことは、じつはちょっとした運動にもなります。
たとえば、次の3つ。
- 駅まで歩くこと
- 駅の階段を上り下りすること
- 揺れる車内で立ってバランスをとること
上記の3つだけでも、体は自然に動いているので、軽い運動として役立ちます。とくに一日中机に向かう仕事をしている人にとっては、通勤中に体を動かすチャンスになります。
| 項目 | 活動内容 | 消費カロリー(目安) | 主な健康効果 |
|---|---|---|---|
| 駅まで徒歩10分往復 | 約1,600〜2,000歩 | 100kcal前後 | 有酸素運動・脂肪燃焼 |
| 駅構内の階段昇降 | 50段×上下2回 | 約20kcal | 下肢筋力・骨密度維持 |
| 車内で立位保持20分 | 揺れに対応しバランス保持 | 約10kcal | 体幹安定・姿勢改善 |
| 遠回りウォーク+5分 | あえて遠いルートを選択 | 約15kcal | 歩数増加・血行促進 |
毎日の通勤に上表のような小さな工夫を加えるだけで、1日あたり120kcal以上のエネルギー消費が期待できますね。背筋を伸ばしてテンポよく歩く、座れそうでもあえて立つなど、意識的な選択で運動効果を高められる点も魅力です。
健康を大事にしたい人は、たまに遠回りして歩く道を変えたり、駅ではエスカレーターではなく階段を選んだりしてみてください。こうした「アクティブ・コミューティング」を続ければ、通勤そのものが毎日の手軽なフィットネスタイムになりますよ。
渋滞や天候に左右される影響度
日本では、梅雨の大雨や台風、大雪など季節ごとに天気が大きく変わります。そのため、通勤手段が外部環境にどれだけ左右されるかは働く人にとって重要ですね。
電車は道路の渋滞には左右されませんが、強い風や大雪が長く続くと、安全のために運転が止まることがあります。バスは道路を走るので、事故や渋滞、雨で道が混むと予定の倍くらい時間がかかることも少なくありません。
| 項目 | 電車通勤 | バス通勤 |
|---|---|---|
| 渋滞の影響 | ほぼ受けない | 信号待ち・事故渋滞で大幅遅延 |
| 雨・小雪 | 地下や高架区間で通常運行が多い | 路面混雑で速度低下が起きやすい |
| 台風・強風 | 安全確保のため運転見合わせが長時間化 | 経路変更や運休が出るが再開は比較的早い |
| 積雪・凍結 | 郊外区間で速度規制や間引き運転 | タイヤチェーン装着で速度低下、最終便繰り上げ |
| 運行情報入手 | 専用アプリとプッシュ通知が充実 | 事業者サイトや停留所掲示で情報更新が遅め |
| 代替手段 | 振替輸送や路線変更が可能 | 近隣ルートが限られタクシー選択が増えがち |
もし、
- 家で仕事や勉強ができる在宅勤務
- 登校・出勤時間をずらせる時差出勤
といった仕組みがあるなら、天気がひどい日は無理に外出しないでリスクを減らすのが安全ですね。
それでも出かけなければならない日は、電車ならほかに走っている路線がないか調べたり、バスならいつもより早めに家を出たりするなど、乗り物の特長に合わせて準備しておくと安心ですね。
バス通勤と電車通勤ではどっちが良いかについてまとめ
この記事をまとめます。
- バス通勤は、自宅や職場がバス停に近い人ならドアツードアで便利
- バスは座れる確率が高く、身体への負担が少ない傾向
- 電車通勤はダイヤが正確で速達性に優れ、乗り遅れても次便がすぐ来やすい
- 電車内では読書やスマホで時間を有効活用できる
- バスは渋滞・事故に弱く、到着時刻が読みづらい場面がある
- 電車は混雑率が高く、密着ストレスや立ちっぱなしの疲労が課題
- バスの運行本数は地域差が大きく、減便リスクにも注意が必要
- 電車通勤は駅まで歩く・立つことで適度な運動が見込める
- 大雨や台風など極端な天候では、バスも電車も遅延や運休の可能性がある
- 定期券はバスがおおむね割安だが、会社の交通費支給ルールで負担額は変わる
- 通勤快適度は混雑状況しだいで大きく上下する
- 費用・時間・快適さ・健康面を総合的に比べることが大切
- バスにも電車にも一長一短があり、絶対的な正解はない
- 最重要なのは、自分の勤務形態や生活リズムに合った手段を選ぶこと
通勤は毎日の積み重ねです。費用を抑えたい、座って楽に行きたい、運動量を確保したい――何を優先したいかは人それぞれ。
まずは自宅と会社周辺の交通インフラ、会社の交通費規定、混雑や遅延のリスクを洗い出し、最もストレスが少ないルートを試してみましょう。

でも、バスと電車、どちらがベストか悩んでいるだけでは、混雑や遅延によるストレスは増えるばかりです。
「通勤は変えられないもの」とあきらめず、今日から試せる方法を探してみましょう。バス停が遠い、電車が混み過ぎる……そんな悩みには、第3の選択肢“パーソナルモビリティ”という答えもあります。
「少しだけ行動を変えてみる」その小さな一歩が、毎日の通勤ストレスをグッと減らすきっかけになるかもしれません。さっそく気になるモデルを見比べて、あなたにピッタリの“ラク通勤”を始めてみませんか?